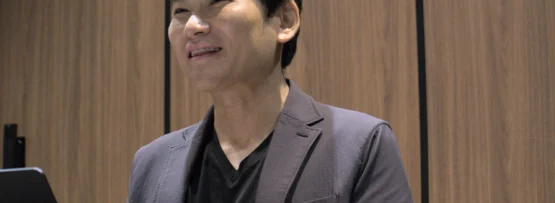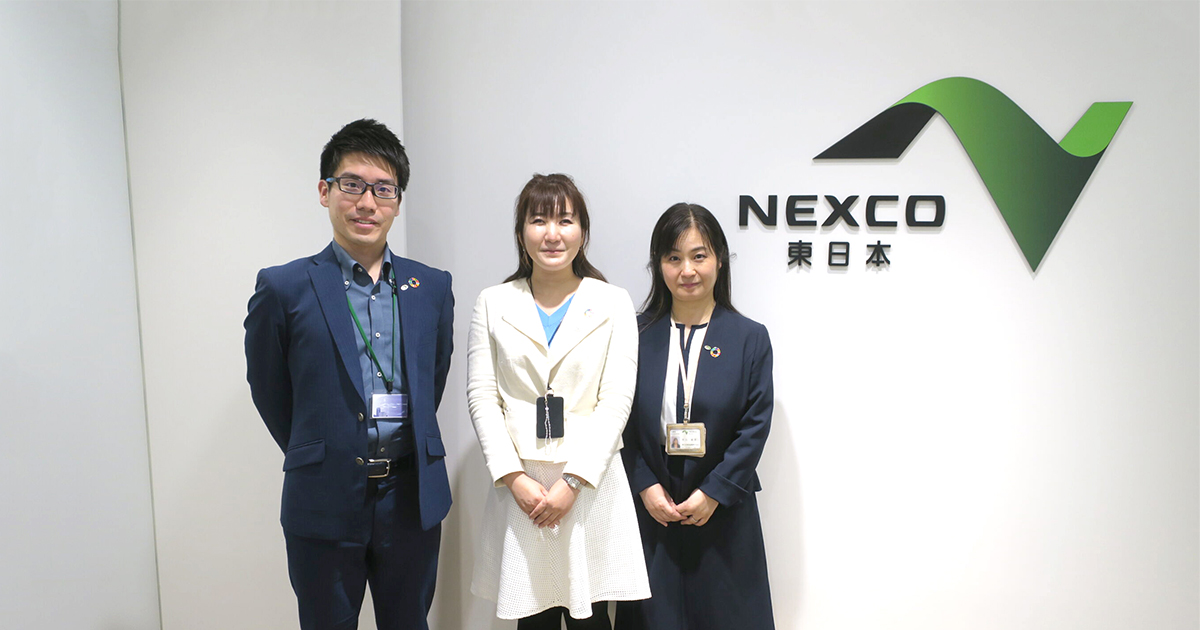電子書籍の流通で日本をリードしながら、地元・徳島を舞台に数々の挑戦を仕掛けてきた経営者がいます。株式会社メディアドゥ代表の藤田恭嗣さんです。
起業家支援や若者の留学支援、地域資源を活かした事業、スポーツ振興——。分野を超えて地域を動かし、徳島の可能性を現実へと変えてきました。
なぜそこまで徳島に力を注ぎ込むのか。
その原点はどこにあり、どんな未来を描こうとしているのか。
ローカルグロース・コンソーシアムの発起人であり、(株)ロケットスター代表取締役の荻原猛がその構想に迫ります。
スピーカー
藤田恭嗣(ふじた・やすし)
株式会社メディアドゥ代表取締役社長 CEO。大学在学中の1994年に起業し、1996年法人化、代表取締役社長に就任。以降、電子書籍流通や出版DXを牽引する事業を展開し、2013年に上場、2017年には徳島に子会社メディアドゥテック徳島を開設。地域と連携した取り組みにも注力し、2020年に起業家支援団体一般社団法人徳島イノベーションベース(TIB)を設立、代表理事に就任。2023年には全国に広がるイノベーションベース(IB)を横断連携する一般社団法人xIB JAPANを設立。2022年には徳島発のプロバスケットボールクラブ「徳島ガンバロウズ」の運営会社、株式会社がんばろう徳島を徳島にゆかりある22社と共同設立。2025年9月には公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)理事にも就任。そのほか、故郷の徳島県那賀町木頭地区で木頭柚子の生産・加工販売を行う(株)黄金の村など複数の事業を展開。経営と地方創生の両軸で挑戦を続けている。
インタビュアー
荻原猛(おぎわら・たけし)
株式会社ロケットスター代表取締役社長 CEO。 大学卒業後、起業するも失敗。しかし起業中にインターネットの魅力に気付き、2000年に株式会社オプトに入社。2006年に広告部門の執行役員に就任。2009年にソウルドアウト株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2017年7月にマザーズ上場、2019年3月に東証一部上場。2022年3月に博報堂DYホールディングスによるTOBにて100%子会社化。博報堂グループにて1年間のPMIを経て、2023年にソウルドアウト取締役を退任。同年4月に株式会社ロケットスターを創業し、代表取締役社長 CEOに就任。50歳で3度目の起業となる。
徳島への想いと歩みの原点
荻原:藤田さんの徳島県での活動は素晴らしい実績というのはもちろん、広い範囲で影響が及んでいると思っています。この地元・徳島への想いというのは、若い頃からお持ちだったものでしょうか?それとも、東京での起業や経営を通じて深まっていったものだったのでしょうか?
藤田:原点は子どもの頃に遡ります。うちは代々400年以上続く家系で、僕はその本家の当主なんですね。物心ついた頃から「お前は跡取りだから」とずっと言われてきました。だから「いずれは帰らなければならない」と自然に思っていた。それが、原点です。
もう一つ大きなきっかけになったのが、父の死でした。1996年9月11日に亡くなったのですが、ちょうど僕が会社を設立したのがその年の4月1日。創業からわずか5ヶ月ちょっと後のことでした。父が亡くなってから49日の法要までの間、ずっと母と一緒に木頭(旧木頭村・きとうそん)で過ごしたんです。そのとき僕は、母が心配なので「会社を畳んで村に戻ろう」と決意していました。けれど、母に「帰ってくるな」と言われたんです。それは衝撃でした。
「力のないあなたが今帰ってきて、何ができるの?」と。
あの言葉はいまもずっと心に残っています。そのとき、強く思ったんです。
「ああ、力がないと、母親すら守れないんだ」と。
じゃあ、「力をつける」って何だろうと考えたとき、自分にできるのは、まずは会社を大きくすることだと。実は、当時は「上場」という言葉すら知りませんでした。でも、創業から3年後に出会った公認会計士の先生から「上場」という概念を教えてもらって、「これだ」と思いました。

「上場すれば、やっと木頭に帰れる」と思って、そこからひたすら走りました。そして2013年11月、東証マザーズに上場。2016年2月には東証一部(現東証プライム)へ変更しました。その年の11月28日、住民票を木頭(現・那賀町木頭)に移しました。家も建て替え、そこからはもうずっと木頭の住民です。僕はよく「徳島を好きな人ランキングがあったら、トップ3には確実に入る」と公言しているんですが(笑)、本気なんです。
人を巻き込んで何かをしようとするときって、自分の根っこがどこにあるのかが問われると思うんです。巻き込まれる側からすれば、「この人の幹はどこにあり、根っこは何で、何を養分にして、何を実らせようとしているのか」が見えないと不安だと思うんです。僕の場合、その根っこは間違いなく徳島と木頭にある。だからこそ、徳島や木頭のためであれば、すべてを捧げる覚悟がある。これまでの僕の歩みを見てもらえれば、それは伝わるはずですし、地元の人も僕を詮索する必要がないんです。
荻原:藤田さんが地元に戻られてさまざまな取り組みを始められましたが、地元の方々の反応はいかがでしたか? 全員が歓迎という雰囲気だったのでしょうか?
藤田:色々な意見はあると思います。
より多くの人に受け入れていただけるよう、コロナ前までは毎年、木頭で事業説明会を開き、メディアドゥとしてだけではなく、柚子の事業や「未来コンビニ」など、地域に関わるプロジェクト全体について説明してきました。来年からまた再開を予定していますし、情報をオープンにして、しっかり共有していくことが大事であり、時間をかけて向き合っていくしかないと思っています。
徳島での挑戦とTIB誕生のきっかけ
荻原:これまで徳島で取り組まれてきた歩みを教えてください。
藤田:一番最初の取り組みは2007年、今から18年前のことです。メディアドゥの事業所を木頭に立ち上げ、7〜8人を雇用しました。現在徳島のサテライトオフィスといえばSansanさんの「Sansan神山ラボ」もありますが、2007年当時徳島にサテライトオフィスを立ち上げたのはうちが第一号だったと思います。

当時は柚子事業にも興味がありましたが、いきなり農業の事業化を進めるのは難しいと感じていました。そのため、まずはメディアドゥの本業に関係する事業所としてメディアドゥ木頭事業所を作ったのです。その次は2013年、メディアドゥの上場半年前の5月に「株式会社黄金の村」を設立しました。この時期には上場の見通しが立っており、本業で一定のところまで力をつけることができたと思い、ここから故郷のための活動を本格化しようと立ち上げたのです。
その後も地域での活動を続け、2018年にはキャンプ場「CAMP PARK KITO」、次に2020年「未来コンビニ」、さらには2023年「NISHIU de repos(ニシウ ド ルポ)」、2024年「PRISM LAB」と、さまざまなプロジェクトを展開しています。
荻原:すでに徳島での活動や拠点を複数設けられていた中、地域一体で起業家を応援する体制でもある「徳島イノベーションベース(TIB)」を設立しようと思われたきっかけは何だったのでしょうか?
藤田:2018年に私はEO Tokyo(Entrepreneurs’ Organization Tokyo)の副会長になり、その後2019年から2020年にかけて、24期の会長を務めました。その際に掲げたのが「SUSTAINABLE EO」というテーマでした。
このテーマを掲げたのには大きな理由がありました。EOは世界的な起業家組織ではありますが、起業家や経営者同士のみが対象のある意味閉ざされた世界です。私が当時の次期会長(23期副会長)時、次期24期の方針を策定するにあたって、EO Tokyoの「会員を増やし規模を拡大するのか」もしくは「クオリティを高めることを重視するのか」のいずれかの方向性でいくべきか、とても悩みました。結果的に「組織には健全な新陳代謝が必要だ」という結論を出し、会員を増やす方向にアクセルを踏みました。
しかし会員を増やすことで沢山の人が入ってくると、当然リスクは増えます。
だからこそEOを持続可能な組織にしていくためには、ただ拡大するのではなく、“社会とのつながり”を明確にし、EOは社会に必要な存在であるという認知を獲得する必要があると強く感じたのです。
そこで私は、「EOが社会から尊敬され、持続可能な組織となること」、そして「EOのメンバーの経営に社会のサスティナビリティを取り込むこと」の2つをテーマに「SUSTAINABLE EO」を掲げたのです。
この中から生まれたのが、「IB(イノベーションベース)という発想」です。EOという組織がサステナブルであるためには、社会との接点を持ち、社会に必要とされる存在でなければならない。その思想が、TIBを構想する最初の原点になりました。

そして、地域や地方に関しては、私自身、木頭や徳島県内で様々な活動を行う過程で「これは結局、自分がいなくなったら終わってしまうかもしれない」という懸念を抱くようになったんです。そこで、次のステップとして「起業家をもっと育て、地域で自走できる人材を増やしていかなければならない」と考えました。一方で、EOには全国、全世界中の起業家や経営者の知見が蓄積されている。この二つが重なったときに、「EOのノウハウを活用し、地域にインストールすることで地方経営者の成長に貢献したい」という想いが生まれました。
IBは「起業家支援」というある意味地域共通のテーマのもと、行政・メディア・金融機関という地域の課題が集まる中核機関三者と連携する座組設計を行いました。まず地域の未来を導く行政に「知って」「後押しして」もらい、金融機関にも理解や支援をしてもらい、メディアには広く発信してもらう。この流れをつくることで「IBの月例会がある」「EOのメンバーが来る」「EOやIBにいる経営者たちは、いい人たちの集まりだ」という認知やイメージを地域で広げていこうとしました。
起業家が起業家を生み育てるとは
荻原:「起業家が起業家を生み育てる」というTIBの理念は、実際のプログラム運営にどのように反映されていますか?
藤田:「起業家が起業家を生み育てる」とは、単なるスローガンではなく、地域の未来をつくるための「切符」だと私は思っています。
地域には行政やメディア、金融機関といったプレイヤーがいて、地域の課題はまずそこに集まってきます。しかし彼らは、起業家ではない。役割上、新しいものをゼロから生み出すことはあまりなじまない。
地域の未来をつくっていくには、やはり新しい挑戦や価値が必要であり、それを生み出せるのはリスクを取ることのできる「起業家」の存在です。地域が未来に向けて変化していくには、起業家の力が不可欠であり、地域の皆さんにはそんな起業家の力を上手く使いこなしてもらいたいと思っています。
行政もメディアも金融機関も含めて、それぞれがそれぞれの立場から「地域の未来をつくる責任」を担っているはずです。だからこそ、私たち起業家が「起業家を育てよう」と旗を掲げることで、皆さんに集まってもらい、手を取り合う理由=大義名分をつくる、そういう設計で私たちは活動しています。
具体的には、ゲスト講師を招く毎月の定例会を通じて地域の起業家や関係者が継続的に集まり、情報交換や連携が生まれています。起業家同士で相談し合えるような人間関係が地域に自然と築かれていくんです。これは単なるネットワーキングではなく、重要なのは、この関係を毎月続けることで関係値もその価値も積み上がっていく点にあります。
たとえば、5年前に参加していた若手起業家が、今や事業を伸ばして社員を雇い、納税もし、国内外へ展開するようになった。そういう姿を見たとき、「あのとき関わると決めたTIBが起業家を生み育てている」とIBを共同設立した銀行さんやメディアさんが実感として喜び合える。それが“成功体験”なんです。多くの人にとって「育てる」とは自分の子どもや部下を育てることのみだと思います。でも、地域一体で起業家を育てることは、それ以上に社会への貢献がはっきりと見える。雇用が生まれ、納税があり、地域経済が循環する。それを自分が関わって生み出せたという実感が大切なのです。
だから私は、「起業家が起業家を生み育てる」という仕組みそのものを、地域を巻き込む「切符」だと思っています。そしてその切符を持った起業家が声を上げ、継続的な活動をしていくことで、地域の中に新たな可能性や相乗効果が生まれ続けていくのです。

荻原:藤田さんが地元に戻られてから描いた新たな構想があれば教えてください。
藤田:僕の第一子が昨年生まれまして、名前は「柚子を愛する」と書いて「柚愛(ゆな)」。木頭になじみのある名前をあえて付けました。今は、家族で木頭で暮らしています。僕はよく東京の人から「ふるさと、帰れる場所があっていいね」と言われるんですが、本当にそうだなと思います。地域で育てられた記憶と帰る場所があるという価値はかけがえのないもの。だから、僕の娘も同じ木頭で育てることを決めました。
もちろん、成長につれて東京の学校やグローバルな環境で育てることも選択肢としては出てくると思います。確かに勉強も大事だし、学びは血肉になる。でも、今の学校教育におけるテスト勉強は「PL(損益計算書)的」だなと感じています。本来の教育って、「何が大切なのか」を知ること。点を取れるかどうかじゃなくて、何を感じ、どう行動するかを身につけることが大事だと思うんです。

僕自身、赤ちゃんと一緒に暮らす中で、日々ものすごく学ばされることばかりです。娘が立って、歩いて、転んで、泣いて……そのひとつひとつが純粋で、美しく描きたいと思うようになりました。
赤ちゃんを育て始めてとても大切なことが2つあるということに気付きました。
1つは「愛された記憶」、もう1つは「帰る場所」。
そして、育てるのは親だけではなく「地育」、つまり地域で育てる。これが僕の中ではすごく大切なキーワードになっています。
都会って便利だけど、「地域で育てる感覚」がどうしても薄れてしまう。でも、人間が生きていく上では、ふるさとの感覚や、誰かに育てられたという実感が必要なんです。だからこそ、地域で育てる仕組みや、地域全体でつながりを持って、例えば都会で生まれて親が若くて育てる力が足りないなどで施設に預けざるをえず「愛された記憶」や「帰る場所」がない赤ちゃんを預かり地域全体で育てていく、今までにない新しい里親制度を本気で作っていきたいと考えています。2026年に木頭から始動します。

地域を動かすスポーツの力
荻原:男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営もされていると伺いました。Bリーグ立ち上げのきっかけや、活動で目指していることを教えてください。
藤田:もともとBリーグを運営するつもりは全くなく、その価値にも気づいていませんでした。転機となったのは、2019年に徳島駅前の総合百貨店「そごう徳島店」が撤退するというニュースです。徳島新聞が「駅前をどうするのか」というテーマで地域の有識者10名に意見を聞くという企画で、そのうちの1人として僕にインタビューいただきました。私が無邪気に「Bリーグを誘致すればいいじゃないか」と発言したことが紙面にでかでかと掲載され、かねてより徳島にBリーグを望んでいたバスケット関係者がその記事に誘発されて本格的に動き始めたのです。
徳島ガンバロウズ発足にあたっては、長年徳島県のバスケ再興を支えていらした県バスケットボール協会の皆様や主要企業の皆様の活動や覚悟に支えられて実現したものにほかなりません。その中で、運営会社(株)がんばろう徳島を徳島にゆかりある22社の皆様と共同設立し、メディアドゥとしては本事業の責任とリスクを取る座組にてスタートしました。
結果として、徳島新聞や四国放送など地域メディアの大きな後押しもあり、わずか2年で黒字化を達成。広告宣伝費はほぼゼロでした。他チームと異なるのは、観客層に60歳以上のご高齢の方と19歳以下が多い点です。これは30~40代に山があるBリーグの平均と比べて明確な違いがあります。会場はおじいちゃんおばあちゃんがお孫さんや家族と一緒に応援し、選手たちへ温かく声をかけ、相手チームにも「よく頑張ったね」と言うほどアットホームな雰囲気に包まれています。こうした空気はSNSなどのwebマーケティングでは作れない、地域メディアとの強い連携で生まれたもので、Bリーグ経験豊富な選手からも「こんなに地域全体で温かく迎え入れてくれるクラブは他にない」と喜んでくれています。

オーナー企業の代表として、私は誰よりも応援します。シーズン中のHOME戦はほぼ全試合に足を運び、マイクパフォーマンスも全力、選手との仲の良さも観客に見せます。「藤田があれだけ声を出して応援しているのだから、私たちも頑張ろう」と観客や関係者に思ってもらえる存在でありたい。それが徳島ガンバロウズを地域一体のチームに育てる一番の原動力になっているのです。
ちなみにチーム名「ガンバロウズ」も当初は大ブーイングでした(笑)。しかし「頑張れ」「頑張ったね」という言葉は、子どもの頃から刷り込まれる、日本人に深く浸透した励ましの言葉です。「未来コンビニ」のネーミングと同様、認知度の高い言葉に小さな工夫を加えた“認知×ギミック”の設計で、今ではすっかり定着しました。
荻原:地域での活動や組織の認知度向上において、特に効果的だった取り組みは何ですか。
藤田:やはり大きかったのは、シーズンインの3年前から始めていたTIBの活動です。TIBは一部の起業家の方々以外には直接関係のない活動ではありますが、開かれた存在であるべく、毎月必ず2回テレビや新聞に取り上げられてきたことで、「どこかで見たことがある」という認知が少しずつ広がっていきました。
そのメディア連携の基盤があったからこそ、そのプラットフォームの上で始まった徳島ガンバロウズにおいてはメディアが発足前から好意的に何度も取り上げていただき、1年目はシーズン213日のうち122日、割合にして57%の日数でメディアに取り上げられ、記事数ベースでは77%。翌年には記事数ベースで約90%を占めました。地方でのローカルメディアの購読率・視聴率はとても高いのでそのインパクトは大きく、露出が増えるたびに試合観戦者も右肩上がりに伸びていきました。
勿論、メディア各社様とは良好な関係づくりのため様々なことに気を配っています。メディアの方々が「取り上げたい」と思えるように、情報はいつでもすぐに出せる体制を整え、イベントの際には必ず声をかける。新しい選手との契約など重要な動きは、必ず事前にメディアへ報告してきました。
メディアの皆さんに限らず、銀行、行政の皆様に対しても徹底して情報共有とご報告を行っています。年2回、6〜8月と年末に必ず徳島新聞、四国放送、阿波銀行、徳島大正銀行、NHKの5社と徳島県、徳島市を訪問し、活動状況をトップに直接報告します。これは単なる情報提供ではなく、社長としてのアカウンタビリティの一部であり、誠実な行動の積み重ねです。こうした継続性が、活動をさらに広げていく大きな原動力になっていると感じます。
地域資源が拓く新たな可能性
荻原:柚子の事業についてもう少し詳しく伺いたいです。柚子という地域資源が、なぜそこまでのポテンシャルを持つと考えているのでしょうか?
藤田:僕、木頭柚子って本当にすごいなと思っていて、売上100億円を達成できるかもしれないと去年、今年くらいに思ったんです。
みかんって海外では「Orange」って言われちゃうんですけど、柚子って「Yuzu」なんですよ。ちゃんと名前が通っている。しかも、みかんのように食べるんじゃなくて、香りを楽しむとか、果汁を使うとか、そういう使い方が多いので、かける手間が他の果物に比べて圧倒的に少ないのが特徴なのです。形が整っていなくても全然いい。農薬も消毒もいらなくなり、草刈りと肥料と剪定と収穫ができれば大丈夫。手間も少なく、やろうと思えば誰でもできる。
たとえば1,000本くらい育てたとして、収穫期は1か月くらい。その他、植え付け・草刈・枝の剪定などで合計1か月。一般企業の会社員の方の年間休日が130日くらいあるとしたら、その中の60日だけ稼働すればいいので、副業としても十分可能なんです。
現在、僕たち黄金の村が村の農家さんから買い取らせていただく柚子の価値を、木1本あたりに換算すると約5,000円なのですが、それを10,000円にしたいと当時父が言っていたことを覚えています。実際、今はグローバル需要がうなぎのぼりで、価格が倍でも仕入れたそばから売れていく状況。1本20,000円くらいまで引き上げて行きたいと考えていますが、展開次第ではそれ以上も狙っていきたいと考えています。ということは1,000本で2,000万円の売上。コストを引いても利益率8割で1,600万円くらい残る。年間2か月の柚子仕事だけでです。

今、グローバルでの柚子のニーズが本当に高く、先日ブラジルの日系農家さんとも契約をしてきました。契約面積は約1,000haで、これは東京の台東区とほぼ同じ広さに相当します。この規模で約60万本の柚子の木を栽培する計算になります。ただ、ブラジルでは柚子は農作物の品種として登録されていないため、このまま栽培しても輸出ができません。そのため現在、日本でいう農林水産省にあたる機関に対し、登録費用を(株)黄金の村の負担で支払い、正式に登録手続きを進めているところです。
こんな風に、木頭という限界集落の果実だけど世界に出ていける可能性がある。地域を愛して、本当に地域の未来を真剣に考え、徹底的に向き合い続けてきたからこそ、この柚子の事業はこれからのポテンシャルが無限大だと確信しています。
活動を通じて感じる喜びと課題
荻原:実際にTIB や徳島での地域共創プロジェクト(木頭柚子、未来コンビニ、CAMP PARK KITOなど)を通じて感じられた“嬉しい瞬間”はどういう時ですか?
藤田:一番嬉しいのは、徳島ガンバロウズの試合を、おじいちゃんおばあちゃんたちが本当に楽しそうに観戦している姿を見たときですね。その笑顔を見るだけで、やってよかったと思えるんです。メディアドゥはBtoBの会社なので、普段は企業の方の笑顔を見ることはあっても、最終的な受け手である地域の方々の表情を見る機会って実はあまりないんです。
僕は木頭という地域に育てられた人間なので、昔お父さんお母さんだった人たちが、今はおじいちゃんおばあちゃんになっていて、そういう方々が「これ食べさせて」と野菜を持ってきてくれるんですよ。それを妻が料理をしてくれる。そのときに「このキャベツはあの家のだよ」「このピーマンはあそこのだよ」って全部言ってくれるんです。そうすると、その情景やおじいちゃんおばあちゃんの顔とかが目に浮かんでくるんですよね。それも嬉しい瞬間です。
毎年、年に2回は地域の家を全部回って、近況報告というより「元気でやってるか?」という顔を見に行くんです。数年前、あるお宅に正月のご挨拶で伺ったとき、その家ではこたつに入ってストーブもつけているのに、ジャンパーを着ていたんです。理由を聞くと「杉が伸びすぎて日が当たらなくなった」と。それを聞いて「これはいかん」と思って、地域の人たちに掛け合って山に生えている沢山の木を切ってもらいました。
上場しても、どれだけ世界に出て行っても、それを語ったところで地域の人とは会話が合わなくなる。だからこそ、“1を1として語れる”関係でいたいんです。地域のおじいちゃんおばあちゃんには、娘を抱っこしてもらって、そのぬくもりを共有して、同じ目線で関係を築いていきたいと思っています。
やっぱりあの人たちの笑顔を見ると、「この人たちのために生きている」「この人たちのために頑張っている」って思えるんです。
荻原:地方(徳島)特有の課題として、人材、資金、情報、ネットワークなどで感じる“壁”は何でしょうか?またそれらをどのように乗り越えてきましたか?
藤田:地方における課題としてよく挙げられるのが、人材や資金、情報、ネットワークの不足ですが、僕自身が感じる壁は、むしろそういった外的なものではなく、「内なる壁」だと思っています。
起業家って、本来人を巻き込む力があるし、動かすこともできる存在だと思うんです。ただ、それをやるかどうか、自分の中でスイッチを押せるかどうか。僕の場合は、たまたま出版やIT業界でビジネスを展開してきたことと、同時に地域の課題解決にも高い解像度で向き合えていたので、「自分がやらざるを得ない」と最初から心から思えた。
でも、東京に憧れて大学や就職で上京し、そのまま東京で自分の世界を作り上げ、そこで成功してきた人たちにとっては、地元で何をすればいいのか分からない、自分に何ができるのか分からない、という「内なる壁」があると思うんです。それを乗り越えられるかが分かれ道だと感じます。
1人ではできないことでも、それぞれ力を持った人たちとつながり、まきこむことで可能になる。そのつながりには地元企業やメディア、行政など、さまざまなネットワークがありますが、それらを動かすには、やはり自分自身がどれだけ時間をかけ、どれだけ大きなインパクトを出せるかが大事になります。
「最小の労力で最大のインパクト」を出す。その“掛け算”を最大化できるのが起業家の力だと思っています。そして、そのためにはまず、自分の中のスイッチを押せるかどうか。それさえできれば、誰でも動き出せると信じています。
次世代を育む取り組み
荻原:今年1月に開催された「うずしおサミット in 徳島-第ゼロ回-」についてお聞きしたいです。また、このサミットから生まれた地域の若者の海外留学支援につながる「徳島県版トビタテ!留学JAPAN」についても詳しく教えていただけますか?
藤田:このサミットは、日本全国や世界からもさまざまな方に徳島へ来ていただき、徳島をはじめとする日本の地方が有するアセットについてグローバルな視点から語り合う場として設計し、今年1月に第ゼロ回として完全招待制で開催しました。外の視点から徳島の魅力や良さを改めて認識でき、結果的に自分たちの地域への肯定感が非常に高まるのが特徴です。
この肯定感は地域の元気につながります。例えば、徳島は本来10の力があるのに、東京と比べるとどうしても5ぐらいにしか感じられないことがあります。しかし、うずしおサミットで外部の人たちと交流すると、実は自分たちの地域が10以上の力を持っていることに気づいたり、感覚的な5の差を埋めようという活力やアイデアが湧き、実際に新しい事業やプロジェクトが生まれたりもしています。

このサミットで議論されたテーマは「地方からのビジネス」「環境」「教育」「文化・芸術」の4つでした。海外の経営者や徳島県内外の経営者、金融機関やメディア、学生、行政、文化人など属性の区別なくフラットに地域の未来について語り合うこのサミットは「徳島版ダボス会議」とも呼ばれました。
うずしおサミットの発起人は、年間1000人以上の海外経営者と会い、インドやベトナムなどの新興国への投資ファンドを経営するBEENEXTファウンダーCEOの佐藤輝英さん、「トビタテ!留学JAPAN」エグゼクティブアドバイザーの船橋力さん、NPO法人ETIC.創業者の宮城治男さんと私の4名です。徳島県後藤田知事とのディスカッションを経て、「うずしおのように皆を巻き込み、熱いうねりを作り出そう」という意義でかねてより知事が提唱されている「うずしお戦略」から「うずしおサミット」という名前が決まりました。
このサミットと「徳島県版トビタテ!留学JAPAN」は、地域の可能性を引き出し、若者の未来を開く大きな起爆剤となっています。
このうずしおサミットのテーマ「教育」をきっかけに生まれたのが「トビタテ!留学JAPAN」の徳島県版です。うずしおサミットの翌日、ゲストを徳島各所にご案内する「うずしおジャーニー」道中のバスの中で、トビタテファウンダーである船橋さんに徳島県版擁立の提案をいただきました。そこで調べてみると、ここ数年、徳島県の高校生の海外留学者数は年間数人程度で全国的に見ても下位であることが分かったのです。
徳島の未来を率いる若者にはより広い視野で世界を見て、世界から日本を、徳島を見てその価値に気づいてほしい、そういった経験を学生のうちから積むことができる若者を増やすことは民間企業や行政の責務だ、と感じました。
「トビタテ!留学JAPAN」は文部科学省が2014年に開始した全国規模のプログラムで、2024年までの11年間で全国で1万1500人以上の学生を海外に送り出しています。留学生は自分で企画を立て、留学計画をプレゼンテーションし、厳しい選考を通過した者たちです。そのため、このネットワークは非常に強い結束力と価値を持ち、全国の留学経験者がLINEなどで日常的に交流しています。
徳島の若者がこの全国ネットワークにアクセスできるようになることで、地域の若者に様々なチャンスが身近にある環境を作りたいと考えています。2025年3月の初旬に知事に直接提案し、わずか1か月足らずで具体的な動きが進みました。
具体的には、徳島にゆかりある民間企業15社が毎年1口100万円ずつ寄附として出し合い合計1,500万円、加えて県も県費として1,500万円を拠出し、併せて約3,000万円の予算を毎年用意し、この資金で約50人の高校生を返済不要の奨学金で海外に飛び立たせる*ことが可能になります。
*留学先や期間により変動
また、資金提供の15社は単なる出資者ではなく、「徳島の教育の未来を考える15社」と位置づけています。徳島を代表する企業、大塚製薬(財団からの拠出を検討)、日亜化学、四国化工機などが名を連ねており、各業界のトップが結集しています。これらの企業が若者を支援し、故郷への誇りとグローバルな視点や価値観を養った子どもたちが将来的に徳島に戻り、地元の企業で活躍してほしいという思いを共有しています。地域の企業に応援され、支えられたという経験は、いずれふるさとに感謝し、肌感覚で地元への愛着を持ってもらうことにも繋がると考えています。
このような動きも、全てはうずしおサミットから、もっとさかのぼると徳島ガンバロウズやTIBによる地域との強固な信頼関係から生まれたものであり、文部科学省の担当者も「ここまで短期間でこれほどの関係者がまとまる県は珍しい」と驚いてくれました。
荻原:そのほかに、未来の起業家を育てるために学生向けに取り組んでいる活動やプロジェクトはありますか?もしあれば、その内容についても教えてください。
藤田:現在、徳島県と徳島大学、そしてメディアドゥで新たな講座を立ち上げようとしています。そこに鳴門教育大学、徳島文理大学、四国大学も巻き込んで、県内の大学を横断した大きな連携をつくろうとしています。その講座の設計は、僕自身のこれまでの経験を言語化して、若い人たちにインストールしていくことはもとより、一般の方にも有料公開講座として開放していくつもりです。
僕が講座で伝えたいのは、地域のためのビジネスやアイデアを成功させるうえで、何よりもまず「愛する故郷、ふるさとを言語化する力」が必要だということです。
よく「お前にはふるさとがあっていいよな」「根っこのある人間でいいよね」と言われます。地元を東京と比較して「どうせ徳島やけん」「徳島やしな」と言ってしまうような空気がありますが、本当に大切なのは、自分が心から「好きだ」と言えるかどうかです。僕は徳島も家族も大好きで、恥ずかしげもなくそう言います。
若い人たちには、ふるさとを定義し特定する能力と言語化能力を身につけてほしいと思っています。自分がどこで育ったのか、それをどう定義するか。その場所には、必ず自分を育ててくれた人たちがいます。その人たちを思い浮かべ、「この人たちに喜んでもらえることをしたい」と心から思えることこそが、それがすべての起点になると信じています。
そして、徳島で何かを生み出すなら、それを全国へ、世界へと広げていく視点が必要。世界を前提として地域のアセットに、テクノロジーやマネジメントを掛け合わせて、どうビジネスモデルを組み立てていくか。それを学び、実践してもらう講座にしたいと考えています。
講座では半年ずつ座学と実地を行います。メディアドゥの電子書籍取次事業やプロスポーツ事業、起業家支援事業や柚子の事業、また別途展開するパティスリー「PRISM LAB」などすべてのプロジェクトでは一貫して全国そして世界を目指していますが、実習ではそれらをどのように設計しているかを実際に見てもらいます。最後にプレゼンをしてもらいますが、何を学んだかをしっかり言語化し、自分の中にインストールしてもらうことを大事にしたいと思っています。

荻原:最後に、徳島や地方で挑戦したい若手起業家や後継者の方々へ、藤田さんが特に伝えたい想いやアドバイスがあればお聞かせください。
藤田:若い起業家や後継者に伝えたいのは、「ふるさとを背負う覚悟が、自分の内なる壁を越える力になる」ということです。僕は、本当にそう信じています。そして、自分の持っている資源やお金は、残しておいても意味がないですから、すべてこの未来のために投資するつもりです。
ふるさとへの愛と覚悟があれば、どんな困難も乗り越えられるはずです。自分の可能性を信じて、一歩ずつ前に進んでほしい。そして、その歩みがやがて地域の未来を切り拓く力になると信じています。挑戦する皆さんを、心から応援しています。
【編集後記】

田中さんの前橋市での取り組みは、単なる地方再生ではなく、一人ひとりの挑戦心に火をつける壮大な実験だと感じました。覚悟の質と量を示し続け、目に見える実績で共感を生み続ける田中さんの行動はまた、経営者としての社会的役割を私たち後輩へのメッセージのようにも思いました。
(クロスメディアグループ株式会社 代表取締役 小早川幸一郎)
【企画・制作】
クロスメディアグループ株式会社
ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がける総合コンテンツ企業。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍、Web、映像など多様なメディアで発信。
(広報室:濱中悠花)