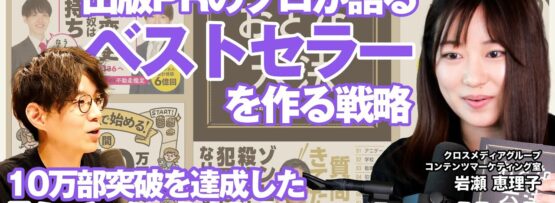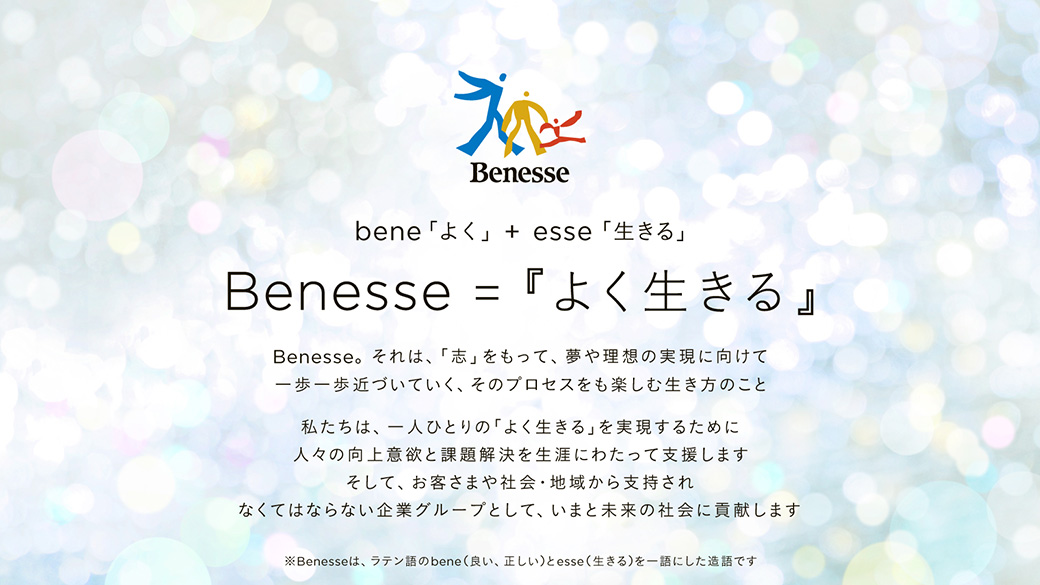静岡県浜松市で生まれ育ち、地域に根づく「やらまいか精神」をベースに、起業家として歩みを進めてきた(株)イノベーション代表取締役社長 CEO 富田直人さん。
東京で同社を創業して上場まで果たした後、「地元に恩返しをしたい」という想いから、静岡県で起業家支援団体や、高校生や大学生への奨学金制度を立ち上げられました。
地方には、東京に比べ起業のノウハウや情報が圧倒的に不足している現実があります。その状況を変えようと、富田さんは自らの経験を地元に還元し、起業家同士が学び合い、支え合う場を創ってきました。
地域の若者が挑戦できる土壌を整えることこそ、富田さんにとっての「自分らしい生き方」であり、静岡県を「ベンチャースピリッツ日本一」の県にすることをミッションに多岐に渡る活動をされています。
富田さんが描くビジョンとその実現に向けた取り組みについて、ローカルグロース・コンソーシアムの発起人であり、(株)ロケットスター代表取締役の荻原猛が伺います。
「やらまいか精神」が育んだ起業への志
荻原:富田さんは、静岡県の浜松市で生まれ育ったということですが、幼少期・学生時代のご経験は、どのように現在の起業・経営・働き方に影響しているのでしょうか。
富田:父が電気工事業を営んでいて、親戚もみな自営業でした。そのため、物心ついたときから、自分も将来は経営者になるのだと考えていました。
ゼロから事業を起こすのではなく、父の電気工事を継ぐつもりでした。そのため子どもの頃から現場を手伝い、一般家庭の工事を請け負う仕事に関わっていました。
進学の際、一時は静岡大学工学部を志しましたが、実家から通いたくない東京に出たいという思いもあり、横浜国立大学に進学することになります。その後、リクルートに入社。3年で退職して家業に戻るつもりでいました。
ところが、父の会社が廃業となり、継ぐことができなくなってしまったのです。
ちょうどリクルート時代に出会ったベンチャー企業の起業家との出会いによって、ゼロから起業することに惹かれていた時期でもあったので、起業の道を選びました。

静岡県浜松市(※鈴木知事とSIB運営メンバーとの会食)
また、そもそも生まれ育った場所にあった「やらまいか精神」も影響していると思います。「やらまいか」とは静岡県遠州地方の方言で、「やってみよう」というチャレンジ精神のことです。
とくに浜松市はこの精神が根強く、スズキ株式会社・ヤマハ発動機株式会社・ローランド株式会社・浜松ホトニクス株式会社といった優良ベンチャーが次々と誕生してきた場所で、起業家精神にあふれる町だといわれています。
この気質は、静岡県内でも西部の特徴です。静岡県では地域によって考え方が異なり、西部は「やらまいか」、東中部は「やめまいか」と言われるように、真逆の文化があります。
地元・静岡県で起業文化を育てる挑戦
荻原:2000年12月に、東京で株式会社イノベーションを設立され、2016年12月には東証マザーズ市場に上場されていらっしゃいます。これまで経営者としての人生を東京で送られてきたわけですが、現在は、SIB(一般財団法人 静岡イノベーションベース)やSIS(静岡イノベーション奨学事業団)を立ち上げられ、静岡県の起業家支援に注力されています。それはどうしてなのでしょうか。
富田:そもそも、私は実家に戻って家業を継ぐつもりでいましたので、東京で事業を展開するなかでも「地元である静岡県に恩返しをしたい」という思いを強く持ち続けていました。
地方には、東京と比べて起業に関する情報・ノウハウ・知識・技術が圧倒的に少ないと感じています。そのため、静岡県のために自らの経験を活かすにはどうするべきかと考え、SIB(一般財団法人 静岡イノベーションベース)やSIS(静岡イノベーション奨学事業団)を立ち上げました。

SIB(一般財団法人 静岡イノベーションベース)で活躍するメンバー
その根底には、起業家精神と「よりよく生きたい」という想いがあります。
ラットレースという言葉がありますが、会社を上場させたとしても経営をするなかで、そのような出口のないサイクルに入ってしまうケースもあります。たとえ社会にとってよい仕事をしていたとしても、会社を大きくすることにとらわれて、そのサイクルのなかで生きることは、本当に自分にとって必要なのかと疑問に思うことが増えました。
私は、自分らしく生きることが大切だと思っています。若いときは全力で走れましたが、年齢も重ねた今、自分の力だけでできることには限界があります。任せる部分を増やし、自分らしく、自分の得意分野で活動したいと考えました。
それが、静岡県でこのような活動をすることだったのです。
荻原:英語でいうと「グローイング・バック・ホームバッグ」という言葉がありますよね。富田さんのように、一度東京に出て成功し、地元に戻るという生き方はとてもクールだと感じます。でも、東京で経営をされてきて、いざ地元に戻ったとき、変化や違和感はありませんでしたか?
富田:違和感はありましたね。経営者が勉強をせずに、営業のための飲み会や食事会が優先されていて、成長よりも忖度が優先される雰囲気を感じたことは少なくありません。大きな成長を目指す人は東京に比べて多くなく、成長してもそれをオープンにする文化もありません。
だからこそ、誰かが成長・成功したらそれをシェアすることで知見にし、みんなで成長するような文化を作りたいと思いました。現在は、起業家同士が学び合い、支え合い、お互いに成長していけるような場を作って活動しています。会社を大きくすることだけが人生ではありませんが、安定した基盤がなければやりたいこともできませんから。
そのためには、若手への起業家精神の醸成も重要だと考えています。だからこそ、一般社団法人SIB(一般財団法人 静岡イノベーションベース)を立ち上げ、静岡県の高校生・専門学校生・大学生に返済不要の給付型奨学金を出すSIS(静岡イノベーション奨学事業団)を作りました。
SIS(静岡イノベーション奨学事業団)では、お金が必要な学生に資金と機会を提供しています。応募者はチャレンジや起業家精神に関して論文を書き、面接を経て支援が決まります。これまで実際が学生5人が起業しました。地元にとって、大きな刺激になっていると感じています。
奨学金は他にもたくさんあるため目立ってはいませんが、それでも私たちが第1歩を踏み出す支援をすることに意味がありますし、起業家がこうした取り組みをすること自体が必要だと思っています。
また、将来は自社株を財団に寄付し、議決権をコントロールしながら配当する仕組みも考えています。
若手支援でベンチャースピリッツ日本一へ
荻原:SIB(一般財団法人 静岡イノベーションベース)では「10年で1000億円」のビジョンを掲げていらっしゃいます。この数字に込めた想いや背景を教えてください。
富田:「10年で1000億円」というのは、「10年でメンバーの合計売上1000億」を意味します。これは、とてつもない高い目標です。しかし、私たちは静岡県を、アントレプレナーシップを持つ「ベンチャースピリッツ日本一」の県にしたいと考えていますから、そのためには非常に重要なビジョンなのです。
現在は4年で100億程度ですが、メンバーの売上を伸ばし、会員を増やしていくことで達成できると考えています。このようなミッションやビジョンがあるからこそ、メンバーもやる気になっています。
ただ、やはり大きなイベントを開催して熱量を上げても、その熱量を維持するのは容易なことではありません。それでも、活動や支援を続けていくことが「ベンチャースピリッツ日本一」への道だと考えています。
地域で起業することは挑戦ですが、私の周りの方々は地元への想いが強いので、東京に行かなくても、同じように、地元で素晴らしい事業を展開できるのだということを示していきたいですね。
こうして活動しているなかで、地元のみなさんやパートナー企業に影響を与えていくことにやりがいを感じています。
荻原:これから静岡県で挑戦しようとしている若手起業家や学生に、どんな言葉を届けたいですか?
富田:これから静岡県で挑戦しようとする若手起業家や学生には、私の地元・浜松市に古くからあった「やらまいか精神」を広めていきたいですね。知事も「やめまいかをやらないかに変えたい」と仰っています。

静岡県は広く、東中部と西部では文化や人柄が違うとよく言われます。浜松市には「やらまいか精神」が根付いていますが、静岡市の方はゆったりしていておおらかな印象があります。しかし、静岡市ならではの性質も、うまく活用することができるはずです。
西部浜松市には、ベンチャー支援制度があり、認定VCやスタートアップに対して4000万円まで出資額を寄付する仕組みなどがあります。当社も認定VCとして関わってきました。浜松市には上場企業も多く、SIBのメンバーも40名ほどいます。業種はさまざまですが、メーカーの跡継ぎの方が3割、IT系が3割、飲食やサービスが3割といった比率です。100年以上続く会社の5〜6代目といった方もいます。
「やらまいか精神」と言うと、浜松市の精神を静岡市の方々へ押し付けているように思われてしまうかもしれません。そのため、「ベンチャースピリッツ」という言葉を選択しました。静岡県一丸となってでもさらなる「ベンチャースピリッツ」を醸成できればと考えています。
若い方々や静岡県に住む方のエネルギーを、内部の対立に使ってしまうことなく、チャレンジ精神やベンチャースピリッツに変えていくことが重要です。
若手起業家や学生には、とくに「ともに、静岡県でこれを実現しましょう」と伝えたいですね。
そうすれば、他の地域にも広がっていくはずです。もちろん、逆に他の地域の取り組みから学ぶことも大切です。
上場を通じた経験を生かす組織づくり
荻原:少し富田さんご自身のお話に戻りたいと思います。起業・上場・地元への貢献など、順風満帆のように思えますが、その過程ではご苦労もあったのではないでしょうか。これまで挫折されたことや壁を乗り越えた印象的な出来事はありますか?そこからの学びがあればぜひ教えてください。
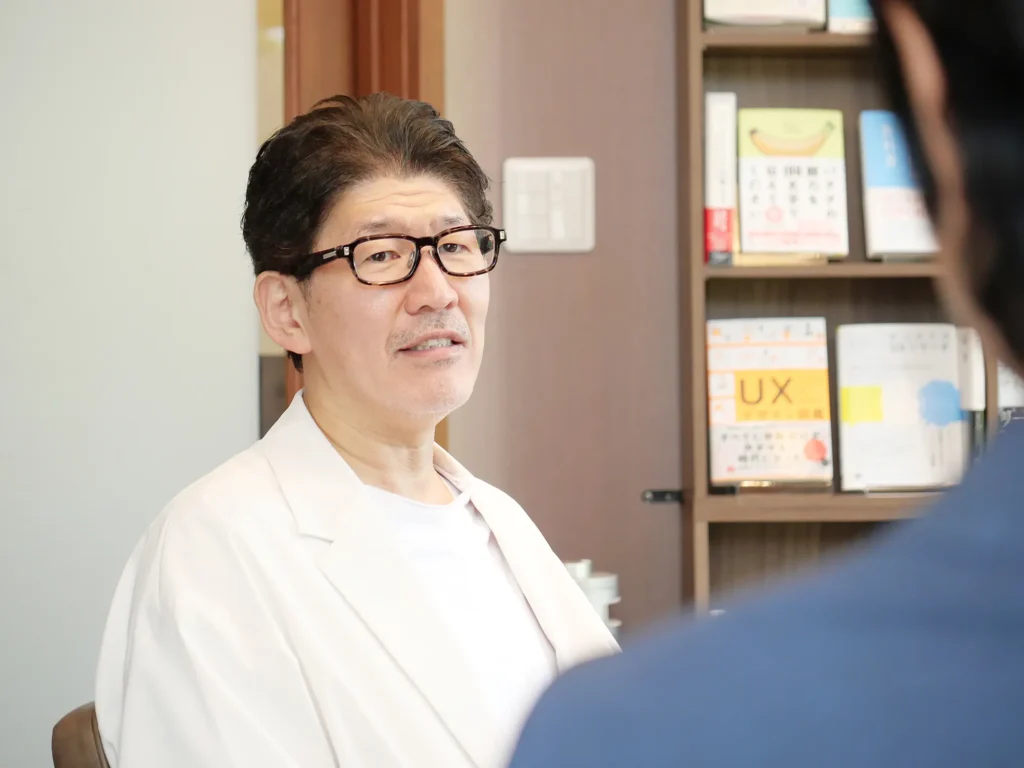
富田:そうですね。とくに上場の過程は大変だったように思います。上場を目指すなら、組織を大きく変えていかなければなりません。いざ上場をしたあとも、本来のミッションやビジョンに関係ない作業が増えます。それによって組織が揺らぐという例は少なくありません。
私の会社でも、上場して1年後に組織崩壊が起きました。多くの社員が辞めてしまった時期もあります。
「人に好かれたい」「みんなから評価されたい」という方もいます。でも、社員・クライアント・株主など、さまざまな人が関わる組織のトップとして、全員に好かれることは不可能だと悟りました。
上場後の経験から、私は「人に何を言われても自分らしく生きる」と改めて決意しました。自分の人生なのだから、全員の顔色を伺うのはやめて、家族や社員などの本当に大切な人との関係を一番大事にしたいと思っています。
そして、短期的にはつらくても、長期的に成功する方法を選ぼうという考えるようになりました。
今でも周囲や時流に影響されることはあります。それでも学びを積み重ねながら、自分らしさを大切にしていきたいと思っています。
荻原:では、組織文化づくりにおいて大切にしていることも、お聞かせください。
富田:主に「起業家精神」と「強みを生かす」ことの2つを大切にしています。
「起業家精神」は、先ほどの「ベンチャースピリッツ」と同義語ですが、もう少し広い意味があります。「ベンチャースピリッツ」が主に新規事業の挑戦やリスクテイクを指すとすれば、「起業家精神」は既存の組織や日常の業務改善においても発揮される、より広い概念です。
「起業家精神」と聞いても、多くの方にとっては「自分は起業していないから」と他人事のように感じられることかもしれません。それに、起業家のように世の中や業界を大きく変える取り組みをするなんて、サラリーマンの立場からすると高すぎる目標に感じられるかもしれません。
でも、どんな職業の方にも起業家精神を持ってもらうことが大切だと考えています。起業家精神は、マインドセットです。すべての大きな変革は1つの小さな改善から始まるものです。だから、改善する文化を大切にして世の中を変えていこうというマインドセットは、どんな立場でどんな仕事をしている方にとっても、素晴らしい結果をもたらすはずです。
「強みを生かす」というのも、組織において欠かせない視点だと思います。
案外、人は強みと弱みがはっきりしているものです。とくに起業家は極端ですよ。営業で突き進むけれども数字は読めないような経営者は少なくありません。私自身は、マネジメントは得意ではありません。
よくジグソーパズルに例えるのですが、社長はパズルの完成形をイメージして、全体像を描く役割です。マネジメント・テクノロジー・マーケティング・人事・広報など、それぞれの強みを生かしながら組織を完成させていくのが社長の仕事です。
そのためには、自分やメンバーの得意・不得意を正しく理解することが重要です。
若手の方は、自分の強みを正しく理解できていなかったり、間違った認識をしていたりすることがあります。そのため「なりたい自分」と「なれる自分」がずれてしまい、苦しくなるのです。それに、教育の影響で、平均点を取るように育つとバランス型を目指しがちです。
でも、私は経験から、強みを生かすマネジメントのほうが成長につながりやすいことを学びました。
だから、社員に対して「あなたはこの分野は得意ではないので、別の役割をやりましょう」と率直に話します。そうすれば、社員は「なぜ自分はこの会社にいるんだろう?」という不安も感じずに済みますから。
5〜10年後、ネットワークで描く成長戦略
荻原:今後5〜10年、静岡県でどんな社会・経済の変化を実現していきたいとお考えでしょうか?そのために必要だと感じていることは何でしょうか?
富田:現在、若手起業家の世界的ネットワークの日本支部「EO Tokyo」 で起業家支援活動を積極的に行っています。5名で毎月理事会を開き、自分の県でうまくいったことをシェアしているのですが、私は静岡県担当です。
このようにメンバーが交流しながら「日本をよりよくするには?」と、知恵を出し合って考えることが、地元に貢献するためにも大切なことだと考えています。
毎月話せる環境があることで成長につながりますし、直接的にビジネスに繋がることも少なくありません。

静岡と他都市を繋ぐイベントを実施
それに、地方にいるとどうしても顧客を地域に限定してしまいがちです。でも、日本全体や世界を視野に入れ、インターネットを活用することで市場は広がります。小さな会社が悪いわけではありませんが、資質があるのに成長させないのはもったいないと思います。
地方から起業家を輩出することは十分可能です。東京にいなくてもいろんなことができます。
ビジネスモデルによっては海外に出られず、数十億規模になれないケースもありますが、もし大きくしたいなら、モデルを変えてピボットする方法もあるのです。
私自身もピボットをしました。当社はもともとコールセンターやリスティング広告の代理店をしていましたが、そこから営業向けの事業に移行して2年で売上1億円を超え、最終的には12億円まで成長しましたし、それでは上場は難しいと判断してすべて売却した経緯もあります。
このような知恵や方法が、日本全体や世界を視野に入れれば見えてきます。だからこそ、私の活動が静岡県の企業や起業家が活躍する足がかりになればと思っています。
そのためにも「LOCAL GROWTH CONSORTIUM」で地方の企業経営者を取材し、ネットワークを作りにも励んでいます。地方には、社会的に価値のあることをされている方は多いのですが、規模は小さいのが現状なので、地方で大きなことに挑戦しているロールモデルを知ってもらいたいのです。
とくに、若いうちからそうした起業家を知ることは非常に大切です。
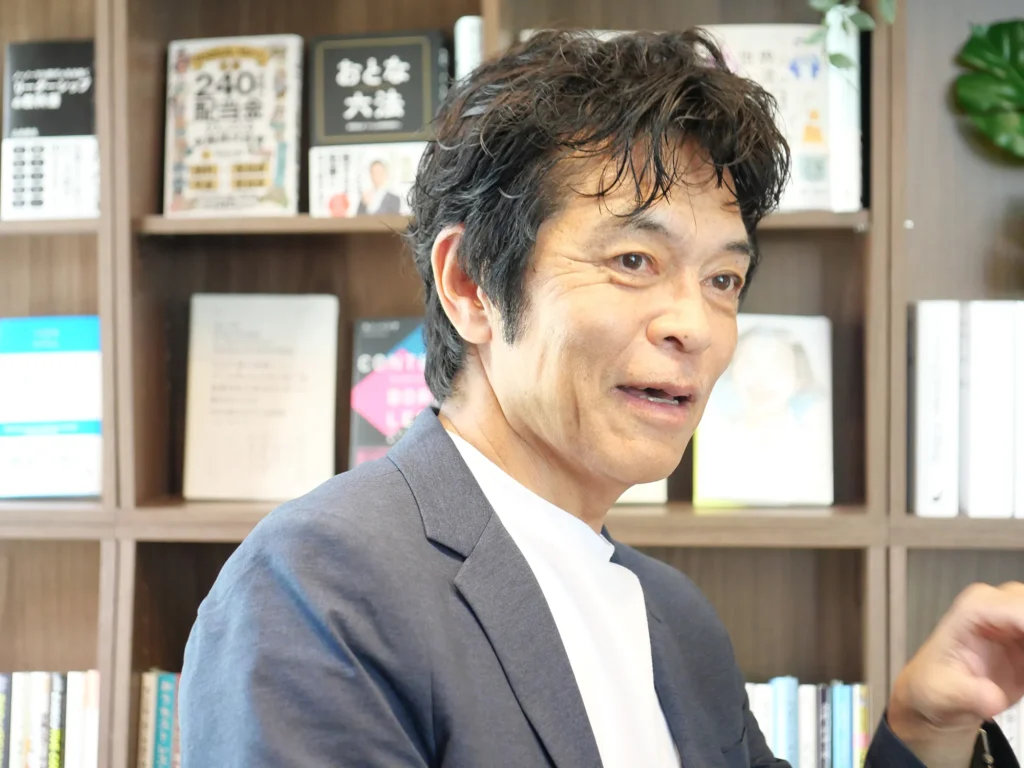
私自身も、20代の頃からそうした出会いに恵まれ、その魅力に惹かれました。東京で会社員時代に起業家と出会い、その人たちの真剣な姿に強い影響を受けました。自分は強い信念を持っているわけでもなく、会社の中で評価されているだけで「ダサい」と我ながら感じ、起業を決意したのです。周りからは「口だけでどうせ起業しない」と言われましたが、それが逆に悔しくて、本当に起業したという経緯もあります。
何より、起業の道を選んで本当によかったと思っています。だから、これからも「仕事を愛する起業家がいる」ということを、若い方々や世の中伝える活動をし続けたいですね。
荻原:富田さんは、メンターとして頼られていることが多いですが、日本全体や世界を広く見て、謙虚さを持って学び続け、常に成長されていらっしゃいます。その姿勢が本当に素晴らしいと感じています。
これからも「LOCAL GROWTH CONSORTIUM」をはじめ、さまざまな場面で富田さんと力を合わせながら起業家育成に取り組んでいければと思っています。本日はありがとうございました。
【編集後記】

田中さんの前橋市での取り組みは、単なる地方再生ではなく、一人ひとりの挑戦心に火をつける壮大な実験だと感じました。覚悟の質と量を示し続け、目に見える実績で共感を生み続ける田中さんの行動はまた、経営者としての社会的役割を私たち後輩へのメッセージのようにも思いました。
(クロスメディアグループ株式会社 代表取締役 小早川幸一郎)
【企画・制作】
クロスメディアグループ株式会社
ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がける総合コンテンツ企業。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍、Web、映像など多様なメディアで発信。
(広報室:濱中悠花)